早めの相続対策を! 個人事業主の事業承継 節税のポイントを解説

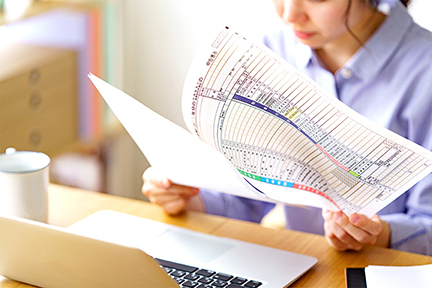 個人事業を承継する方法としては、事業主が亡くなってから「相続」という形で引き継ぐ、事業主の生存中に「贈与」という形で引き継ぐ、または「売買」によって第三者などへ事業承継する方法があります。
個人事業を承継する方法としては、事業主が亡くなってから「相続」という形で引き継ぐ、事業主の生存中に「贈与」という形で引き継ぐ、または「売買」によって第三者などへ事業承継する方法があります。
親から子へ個人事業を引く継ぐときには、相続か贈与による承継になりますが、贈与による承継であれば、親が生存中に子へ事業を引き継ぐことができるため、仕事のノウハウ、ビジネス上の人脈なども同時に承継することができます。そのため、事業がよりスムーズに移行できると考えられます。
しかし、親から子へ事業を承継するときに発生する贈与税について心配されている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、親の行っている個人事業を贈与により子に承継する際の手続きや税金対策について解説します。
贈与による事業承継のメリット
「贈与」による事業承継のメリットは、前事業主の生前に準備が進められるためスムーズな事業の引き継ぎが可能になるということです。
「相続」による承継は、遺言書がない場合などでは、事業が遺産分割協議の対象となってしまう可能性があり、一時的に事業がストップしてしまうという心配があります。最悪のケースでは、事業自体が承継できないこともあり得ますが、生前に贈与という形で承継しておけば最悪の事態を避けることができるでしょう。
また、贈与税、相続税対策について準備期間を持てることも利点といえます。
贈与による事業承継に必要な手続き
個人事業の贈与はどのように行うのでしょうか。
個人事業の贈与は、親から子へ名義を変更すれば完了という単純なものではありません。
一旦、親の行っていた事業を廃止し、新規に子が事業の開始を届けるという事務作業が発生します。
1.承継する人(親)の「廃業届」を提出
親の行っている個人事業の「廃業届」を税務署へ届け出ます。また、青色申告の承認を受けていた場合は、「所得税の青色申告の取り止め届出書」も提出します。
2.承継される人(子)の「開業届」を提出
親の廃業届に続いて、承継される子側の「開業届」を税務署へ提出します。なお、開業届には「屋号」を記載する欄がありますので、親の屋号を引き続き使用することは可能です。同じ屋号を使えば取引先にも事業承継が伝わるでしょう。
なお、「所得税の青色申告承認申請書」も改めて提出する必要があります。
つまり、個人事業の承継は、事業の中身は承継しても、手続き上は、親の事業を廃止して、子が新しく事業を興すことになります。
贈与による事業承継の税金対策
個人事業主であっても、固定資産、事業用預貯金、商品など、事業資産を引き継ぐことになれば贈与税がかかります。
事業を承継された後継者は、受け継いだ資産の評価額に応じた贈与税を払うことになりますので、納税資金についても考えておく必要があります。
そこで事業承継によって発生する贈与税対策について考えてみましょう。
贈与税を軽減する方法
1.暦年贈与の活用
年間110万円までの贈与は非課税となる制度です。贈与額が110万円を超えてしまうと、超えた金額に累進課税方式で税金がかかります。
つまり、贈与額が多いほど課税率が上がるため、納める税金が高くなります。
より多くの非課税枠を利用するためには、数年に分けて資産を移動させることが得策です。
そうすることで、毎年110万円の非課税枠が利用できます。
2.相続時精算課税の活用
年間の非課税枠が110万円の暦年贈与に対して、累計2,500万円までの贈与に対して贈与税が免除される制度が相続時精算課税の特徴です。
贈与額が累計2,500万円を超えてしまうと、超過額に一律20%課税されることになりますが、一度に多額の事業資産を移動させたいときには有用な方法となり得ます。
しかし、この制度により取得した財産は、前事業主(贈与者)である親が死亡したときには、贈与時の評価額を相続財産に含めて相続税を計算することになります。
つまり、正確にいうと贈与税が免除されるというより納税を先延ばしにしておいて、最後に相続税で精算する制度であることを理解しておく必要があります。
また、暦年贈与と相続時精算課税は併用できません。
相続時精算課税を一度選択したら、暦年贈与に戻れませんので、どちらを選択したほうが得なのか慎重に判断してください。
3.不動産は贈与ではなく使用貸借にすると贈与税がかからない
事業資産のうち評価額が大きくなりがちな土地や建物などの不動産を贈与してしまうと、後継者に多額の贈与税の支払い義務が生じてしまいます。
そこで、不動産については贈与をせず、所有権を前の事業主(親)のままとしておいて、後継者は、親から土地・建物を貸借する形をとれば、とりあえず贈与税は発生しません。
使用貸借でも、実際の不動産の使用者は後継者ですので、不動産にかかる固定資産税や修繕費などは経費として計上することが可能です。
ただし、この方法も一時的に納税を先延ばししている形です。
所有者の前事業主(親)が死亡し後継者がそのまま不動産を相続することになれば、相続税の課税対象になります。
しかし、相続時には、一定の要件を満たすことで「小規模宅地の特例」という土地の評価額が最大80%減額できる制度が適用できる場合があります。特例を利用できれば、大幅に相続税を抑えられます。
将来的に土地を相続する際に、「小規模宅地の特例」の適用要件を満たしているのか、あらかじめ確認しておくことも大切です。
4.個人版事業承継税制の活用
個人版事業承継税制とは、青色申告者の事業を後継者へ贈与する場合に、一定の要件を満たすことで贈与税が猶予され、さらに、贈与税が猶予されている後継者が死亡した後には、猶予されていた贈与税が免除されるというお得な制度です。ただし、期間限定です。
具体的には、2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、かつ、2028年12月31日までに後継者が贈与によって特定事業用資産を取得した場合に限り適用されます。
特定事業用資産とは、400㎡以下の宅地、床面積800㎡までの建物、その他固定資産税の減価償却対象とされている固定資産などです。
後継者が20歳以上であること、贈与の日までに3年以上事業に従事していることなど要件はありますが、この制度を活用することで、実質、贈与税や相続税はかからないことになります。近々事業の贈与を考えている方にとっては、非常にお得な制度となります。
なお、相続にて事業を承継した場合も、同様の制度が活用できます。
後継者は課税売上1,000万円超えても2年間免税事業者のまま
最後に個人事業主の消費税について説明します。
個人事業主の中には、消費税の納税義務のある課税事業者と、納税を免除されている免税事業者があります。
線引きは、課税売上が1,000万円を超えているかどうかです。そして1,000万円は今の売上ではなく2年前の課税売上で判定します。
しかし、仮に、前事業主である親が課税事業者であって、事業を引き継いだ後継者である子も課税売上が1,000万円を超える見込みであったとしても後継者は2年間免税事業者でいることが許されています。
なぜなら、後継者は新規に事業を起こした場合と同じ扱いになるため、2年前の売り上げはないものとされるからです。
一方、相続により事業を承継した場合は、例外的に事業を継続して行っているものとさるため、後継者の2年間の免税措置はありません。
つまり、課税事業者の事業を承継する場合には、単純にいうと、相続より贈与で承継したほうがお得といえるのです。
まとめ
個人事業主が自分の事業を子や孫へ引き継ぐ際の主な手段としては、相続によるものと、贈与による方法があります。
本記事では、贈与という形で事業を承継する場合について解説しました。
何も策を講じないで贈与により事業を承継すると、後継者に多額の贈与税が降りかかる場合があります。
税金を抑えるための制度はさまざまありますが、どの制度が利用可能かは個別に検証する必要があるため、一概にいうことができません。
また、相続時に発生する相続税を見越して、贈与の手段を考えておくことも大切になってきます。
事業承継に不安がある場合は、専門家へ相談し適切なアドバイスを受けるのも一つの方法です。
参考:国税庁 個人の事業資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
0022005-016_04.pdf (nta.go.jp)
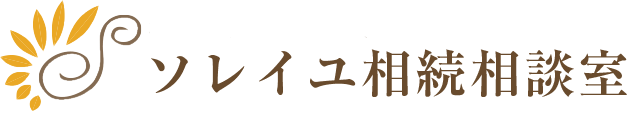

![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/i3yJKUMIzTRrl5P5ZZwwE72aLnQPaJNKyCHscKlV.png)
![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/e1LEOFAUxAAEyA54anKQHuSbRHnk8oBBDc98qad2.png)




![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/YBinHyDM8hpRvWbTTFZXCAFHOfS8wEI3m6twFq0Q.png)









