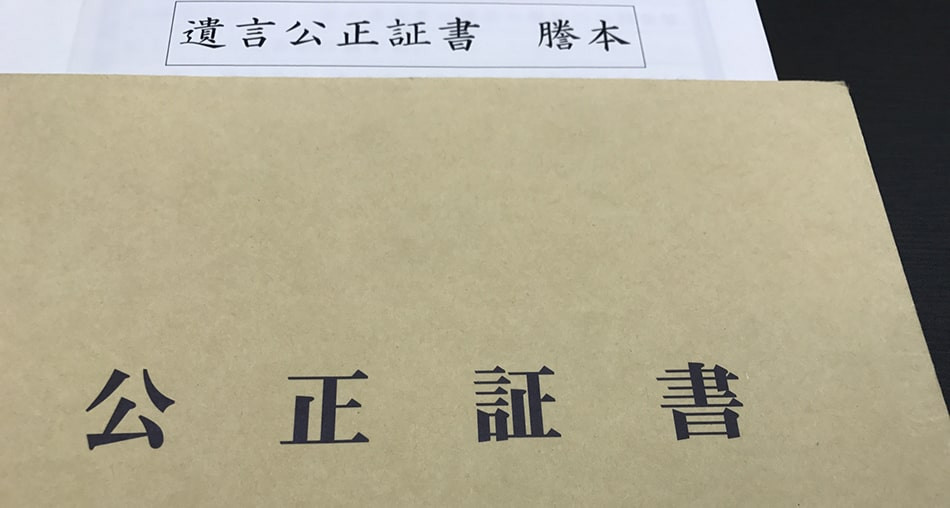わかりやすい相続税の基礎控除
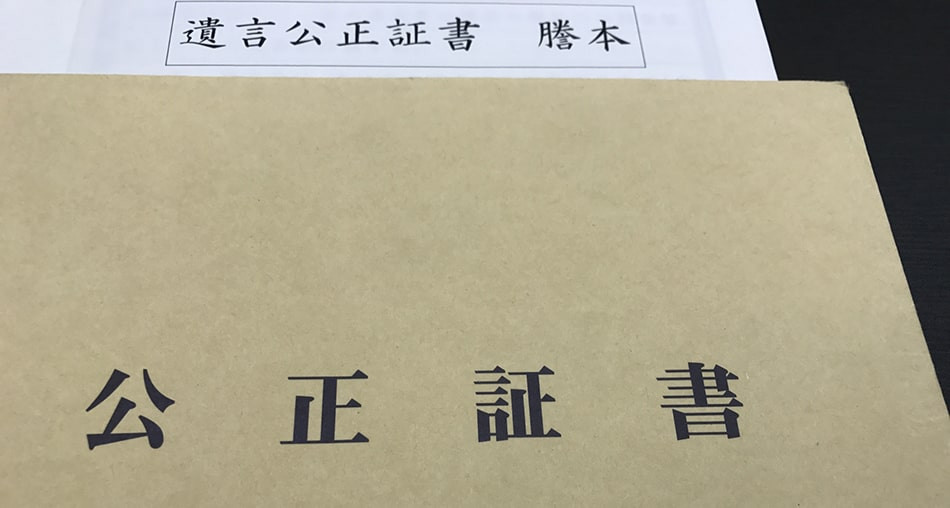
相続税には「基礎控除」という制度があり、被相続人の財産がこの基礎控除額を超えない範囲であれば相続税がかからない仕組みになっています。
基礎控除を知ることは、相続税がかかるかどうかだけでなく、生前の相続税対策にも役立ちますので、ぜひこちらの記事を参考にしてください。
(目次)
被相続人の財産を相続する際、その財産には相続税がかかります。しかし、相続財産の全額に相続税が課されるわけではありません。
相続税には一定の金額までが非課税になる「基礎控除」という制度があります。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。
相続財産の額から基礎控除を差し引き、残った部分にのみ相続税がかかる仕組みですので、相続財産の額が基礎控除額よりも小さい場合は相続税がかかりません。
例えば、被相続人には7000万円の財産があり、法定相続人が妻と2人の子供のみのケースを考えてみましょう。
法定相続人は合計で3人ですので、このケースの基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。
したがって、相続財産7000万円から4800万円を差し引いた2200万円に対して相続税がかかることになります。
計算式から、相続税の基礎控除額は法定相続人の数が多ければ多いほど高くなるようです。
では、法定相続人とは一体どのような人でしょうか。次から見ていきましょう。
法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を相続することが認められた相続人のことです。
法定相続人になれるのは「配偶者」と「血族」のみで、被相続人の配偶者は常に相続人になることができます。
血族相続人には優先順位があり、順位の高い人から相続人になります。
なお、被相続人の子が被相続人よりも前に亡くなっており、亡くなった子に子(被相続人からみた孫)がいる場合は、孫が亡くなった子の代わりに相続人になります。
被相続人に子や孫がいない場合は、父母や祖父母が法定相続人になります。
父母と祖父母がどちらも健在であれば、被相続人に近しい人(この場合は父母)が法定相続人となります。
被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続します。
被相続人の死亡の時における遺産(みなし相続財産など一定のものを含みます。)の合計額から負債の金額を控除した正味の遺産額が基礎控除以下であったときは、相続税の申告書を提出する必要はありません。
もちろん相続税が課税されないわけですから納税も発生しません。
ただし、配偶者税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を受けるためには相続税の申告書の提出が要件とされていますので、特例適用後に基礎控除以下となった場合でも申告書の提出が必要です。
法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、相続税の基礎控除を計算する上では実子と同じ扱いとなります。つまり、養子も第1順位の法定相続人であるということです。
ただし、法定相続人として数えることができる養子の数は無制限ではありません。
被相続人に実子がいる場合は、法定相続人になれる養子の数は1人のみ、被相続人に実子がいない場合でも、数えられる養子は2人までと制限されています。
例えば、被相続人に配偶者と1人の実子、2人の養子がいるケースを考えてみましょう。
被相続人には実子がいるため、相続税の基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は「配偶者1人+実子1人+養子1人」の合計3人となります。
したがって、実際に遺産分割をするのは配偶者1人+実子1人+養子2人の合計4人だとしても、基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円となるのです。
被相続人よりも先に亡くなっている法定相続人がいる場合は、「代襲相続」が発生します。
この代襲相続が発生すると、法定相続人が増える可能性があります。
代襲相続とは、法定相続人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、亡くなった法定相続人の子が代わりに相続することです。
亡くなった法定相続人が子の場合は孫が、兄弟姉妹の場合は甥・姪が代襲相続人となり、孫や甥・姪が複数人いる場合は全員を法定相続人として数えることができます。
例えば、被相続人には既に亡くなっている子がおり、その子には3人の子(被相続人からみた孫)がいるケースを考えてみましょう。
本来、被相続人の子が生きていれば法定相続人は1人ですが、被相続人の子は亡くなっているため代襲相続が発生し、3人の孫が法定相続人になります。
相続欠格や相続廃除に該当する場合、その法定相続人は相続権が剥奪されてしまいます。
相続欠格とは被相続人の相続に関して不正をはたらいた人などが相続人になることをできなくする制度のことで、相続廃除とは被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた人を、相続人から廃除する制度のことです。
これらに該当する人は、相続税の基礎控除額の計算上の法定相続人にカウントすることはできません。
例えば、被相続人には妻と長男、次男がいるが、長男が被相続人に対して家庭内暴力等を行っていたケースで考えてみましょう。
長男に対して相続廃除が認められると、法定相続人は配偶者と次男の2人になります。
この場合、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円となります。
相続税がかかるかどうかを判断するためには、相続税の対象となる相続財産を洗い出す必要があります。
相続といえば、預貯金や不動産など相続する人にとって利益となる財産に関心が集まりがちですが、相続税の対象にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
では、相続税の対象となる財産には具体的にどのようなものがあるでしょうか?
被相続人名義のもの以外にも、家族や他人の名義になっていても実質は被相続人に帰属する場合もありますので注意しましょう。
また、有価証券も相続税の対象となる財産です。有価証券には公社債、株式、投資信託など様々な種類があります。
土地や建物などの不動産、土地の上に存在する権利も相続財産に含まれます。
土地には、宅地、農地、山林、原野、牧場などの種類があり、建物の場合は、戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家などがこれに該当します。
また、土地の上に存在する権利(所有権、借地権、定期借地権、地上権)なども相続財産に含まれます。
動産には大きく分けて「家庭用」と「事業用」の2種類があり、事業用動産とは機械や器具、社用車、棚卸資産など、個人事業のために使い、それにより生じた財産のことです。
被相続人が亡くなったことにより相続人に支払われる死亡保険金や死亡退職金は、被相続人の財産ではないため、本来は相続財産には含まれません。
しかし、相続税の計算上は、死亡保険金や死亡退職金も相続財産に含めて計算されるため、「みなし相続財産」といわれています。
なお、死亡保険金が相続税の対象となるのは、保険料の負担者が被相続人で、保険料を受け取るのが相続人の場合に限られます。
また、死亡退職金の場合は、被相続人の死亡後3年以内に支給された退職金のみが対象です。
これまでご紹介したものの他にも、相続税の対象となるプラスの財産は多くあります。
例えば、ゴルフ会員権、著作権、特許権、占有権、漁業権、形成権、知的財産権などです。
また、税金の還付金債権、慰謝料請求権、損害賠償請求権、第三者への貸付金債権などもプラスの財産に該当します。
借入金とは、例えば住宅ローンの残高債務、車のローン、クレジット残債務などがあります。
また、未払金には土地や建物を借りていたときの賃料や光熱費、携帯料金、管理費、リース料、医療費などが挙げられます。
保証債務は、いつ債権者から支払請求をされるのか不明で、請求されたとしても主たる債務者に求償することができるため、原則として相続税の計算に含むことができません。
所得税や消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、延納していた相続税、贈与税などもマイナスの財産に該当します。
被相続人が土地や建物を貸していた場合は、借主から敷金や保証金を預かっている可能性があります。
また、被相続人が事業を行なっていた場合は、買掛金や前受金が存在する場合もあります。
祭祀財産とは、仏壇や墓石など神仏や先祖を祀るために必要な道具のことで、普通の相続財産とは区別されます。
一般的に、相続が始まると不動産などの財産は相続人間で分けることになりますが、祭祀財産は複数の相続人で共有することができないため、特定の人が引き継ぐことになっています。
したがって、祭祀財産には相続税がかからないことになっています。
ただし、これらを商品として取り扱っている場合や、骨董的な価値がある場合は相続税の対象となります。
被相続人の一身に専属した権利義務については、相続することができないため相続税はかかりません。
一身専属権とは、その性質上、被相続人でなければ認められない権利や義務のことをいいます。
例えば、離婚請求権や年金受給権、弁護士や司法書士などの資格がこれに該当します。
今回は、相続税の基礎控除の計算方法やケース別注意点、相続税の対象となる財産についてご説明いたしました。
相続税額を計算する上で、「法定相続人は何人いるか」「どのような財産に相続税がかかるのか」を知っておくことは非常に重要です。
また、1-2でご説明したとおり、配偶者税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を受けると相続税がかからなくなる場合には、相続税申告が必要となるので注意が必要です。
いざ相続が発生してから慌てることのないように、今から相続の知識を身につけ、スムーズな相続を実現しましょう。
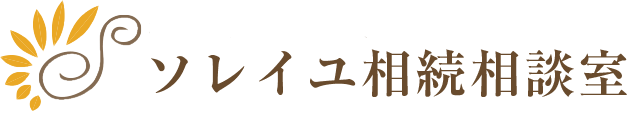

![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/i3yJKUMIzTRrl5P5ZZwwE72aLnQPaJNKyCHscKlV.png)
![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/e1LEOFAUxAAEyA54anKQHuSbRHnk8oBBDc98qad2.png)




![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/YBinHyDM8hpRvWbTTFZXCAFHOfS8wEI3m6twFq0Q.png)