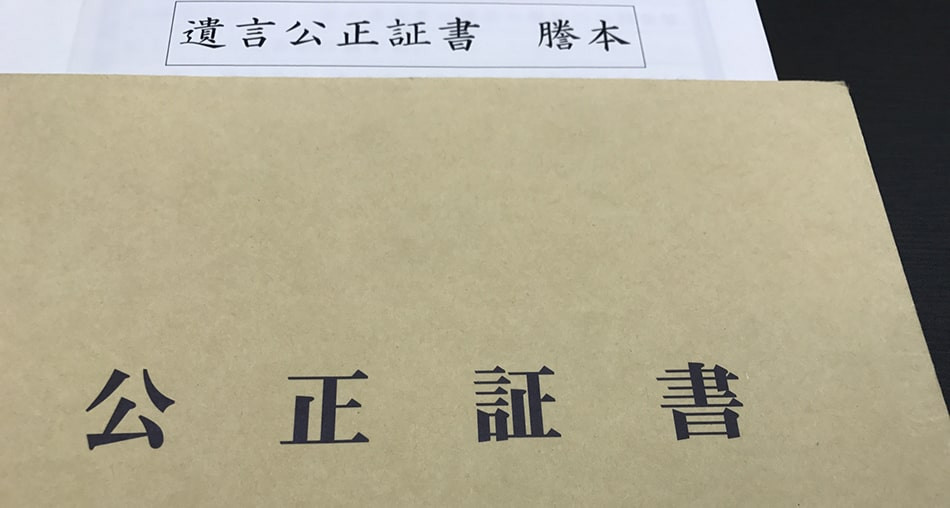課税額ゼロでも相続税申告は必要? 申告書提出義務があるケース&ないケース

 「課税額がゼロなら相続税申告は不要」と考えるのは間違いです。申告書の提出が必要なくなるのは、基礎控除等、一定の状況で広く適用される税制しか使わない場合に限られます。配偶者や居住用不動産にかかる特例等を使うつもりなら、必要事項を記載した申告書を出さない限り、適用したものとはみなされません。
「課税額がゼロなら相続税申告は不要」と考えるのは間違いです。申告書の提出が必要なくなるのは、基礎控除等、一定の状況で広く適用される税制しか使わない場合に限られます。配偶者や居住用不動産にかかる特例等を使うつもりなら、必要事項を記載した申告書を出さない限り、適用したものとはみなされません。
後になって無申告を指摘されると、各種制度による減額がほとんどない課税される上、所定の割合で加算した額を納めることになります。判断は早まらず、以降の解説に沿って状況を切り分けてみましょう。
❏相続税申告が不要になるケース
相続税法第27条1項によると、一定の控除によって課税額がゼロになれば、その時点で申告書の提出義務は生じないと判断できます。以下のリストで紹介するのは、条文で挙げられている控除の名称です。
・基礎控除
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・相続時精算課税による贈与税額控除
税額軽減につながる制度は何種類も存在しますが、ここで挙げるものは税の負担の公平化を目的として導入されています。特定の財産や相続人について承継を支援するというより、一定の状況に対して納税資金の負担調整を図るものである点から、申告書の提出有無に関わらず自動的に適用すると考えます。
それぞれの事例に当てはめて判断できるよう、相続税の申告書を出さなくても良いケースを具体的に挙げてみましょう。
課税遺産総額が基礎控除額の範囲内である場合
相続税申告書の提出が不要になるケースの代表格は、課税対象になる財産の合計額(=課税遺産総額)が基礎控除の範囲内に収まる場合です。基礎控除は「無条件で相続税がかからない範囲」であり、以下の方法で計算できます。
▼基礎控除の計算式
3千万円+600万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日以降の相続開始分より適用
▼申告不要となる例
課税遺産総額が4千万円、民法上の相続人の範囲が妻と子2人の計3人である場合
※3千万円+600万円×3人>4千万円
障がい者や未成年者が財産を取得する場合
法定相続人が障がい者や未成年者だった場合、その人の分の課税額について一定の控除があります。その結果として相続人全体の相続税額がゼロになった場合も、申告書を提出する義務は負いません。
▼障がい者の税額控除の計算式の計算式
控除額=10万円※×満85歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)
※寝たきり状態等、特に症状の重い「特別障害者」に該当する場合、1年あたり20万円に増額されます。
▼未成年者の税額控除の計算式
控除額=10万円×満20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)
▼申告不要となる例
相続税の計算を行ったところ、56歳の障がい者と母親で各120万円ずつと分かった場合
※10万円×29年=290万円の税額控除につき、余った部分を母親の課税額に適用
前回の相続から10年以内である場合
同年代の夫婦やきょうだいの間では、同じ財産について立て続けに相続税が課税されると考えられます。夫婦の場合だと、夫が亡くなって妻が税を支払い、その妻が亡くなって子が税を支払う……といったイメージです。
上記のようなケースでは、被相続人(=亡くなった人)に課された過去10年以内の相続税につき、一定の額を今回の相続税から控除する制度が適用されます。この「相次相続控除」によって今回の課税額がゼロになる場合も、申告書の提出義務はありません。
▼相次相続控除の金額の考え方
前回被相続人に課された相続税額のうち、1年が経過するごとに10%の割合で逓減した(=段階的に少なくした)後の金額
国内居住者が外国にある財産を取得する場合
日本に生活拠点を持つ人が国外財産を取得したケースでは、二重課税にならないよう、現地国での納付分を内国税から控除する制度が使えます。この「外国税額控除」で課税額がゼロになった場合も、国内で申告書を提出する義務はなくなります。
▼外国税額控除の金額の考え方
・外国で納めた相続税相当の税
・日本の課税額のうち、相続財産に占める国外財産の割合に相当する分
→①・②のいずれか少ない方の金額
❏課税遺産総額の考え方│生前贈与や保険金に要注意
申告書提出の要否を正しく判断できるのは、課税額の計算が合っている場合に限られます。計算で注意したいのは、相続税がかかる範囲、すなわち「課税遺産総額」です。この計算の起点となる数値が間違っていると、どう進めようと正しい相続税額は出てきません。
以降で説明する財産は、いずれも課税遺産総額の内訳に含まれます。勘違いや見落としがないよう、いま一度確認しておきましょう。
生前贈与
生前のうちに譲り受けた財産は、原則として課税遺産総額に含めなくてはなりません。その範囲には制限があり、贈与の状況によって異なります。
▼課税遺産総額に含める生前贈与
・相続開始前3年以内の生前贈与
・相続時精算課税※を適用した後の全ての贈与価格
※60歳以上の被相続人から20歳以上の子・孫への贈与を対象に、基礎控除額と税率を優遇し、その代わりに将来における相続税の課税(=精算)を行う制度です。
みなし相続財産【死亡保険金等】
相続税の課税対象になるのは、生前贈与と相続財産だけではありません。死亡によって得た利益の状況から、相続や遺贈で取得したと「みなされる」財産も課税遺産総額に組み入れられます(下記具体例)。
・死亡保険金※
・死亡退職金※
・免除された債務
・定期金に関する権利(個人年金等)
・低額で譲り受けた財産(時価と譲渡価格の差額)
・信託受益権(信託財産から給付等を受ける権利)
※課税遺産総額に算入するのは「500万円×法定相続人の数」を超える部分のみです。
❏課税額ゼロでも相続税申告が必要になるケース
結果的に納めるべき税がないとしても、これまで挙げなかった控除・特例を適用するのであれば、相続税申告書の提出は必須です。
以降紹介するいずれかの状況に当てはまる人は、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月目)に向け、余裕を持って申告書の作成に着手しましょう。
配偶者の税額の軽減を適用する場合
亡くなった人の法律上の妻や夫が受け取った財産は、法律で定められる取得分(=法定相続分)まで課税されません。
この「配偶者の税額の軽減」を適用する時は、遺産分割を終えた上で、相続人の範囲と財産取得の状況を申告しなければなりません。
参考:相続税法基本通達27-1
小規模宅地等の特例を適用する場合
持ち家や経営中の賃貸アパートを相続する場合、小規模宅地等の特例による評価減があります。ただし、居住継続等の一定の要件があり、減額の範囲にも限度があります。
相続した宅地等の状況を相続税申告書に記入して提出しなければ、適用は認められません。
各種納税猶予の適用がある場合
自社株や農地の相続では、免除を予定して納税猶予を行う制度があります。制度利用にあたっては、財産を取得した人による営業継続等の要件を満たさなくてはなりません。
適用のパターンとしては、①今回の相続で納税猶予を受ける場合、②前回の相続または贈与における猶予分を免除してもらう場合の2つが考えられます。①と②のどちらであっても、納税の有無に関わらず、相続税申告書を提出しなければなりません。
▼紹介した制度の名称
・事業承継税制(法人版・個人版)
・農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
贈与税額控除がある場合
生前贈与があってなお課税額がゼロになるとしても、相続税の申告書が必要になるケースがあります。贈与税額控除により、すでに支払った税を相続税額から差し引き、二重課税を避けようとする場合です。
例外的に、控除できる贈与税額が「相続時精算課税」の適用分しかないケースでは、申告書の提出義務はありません。個別ケースでの判断は、過去の税務資料をさかのぼって確かめてみる必要があります。
❏相続手続きを正しく終えるためのポイント
相続税に関する手続きは、亡くなった後の一連の業務の最後に行うものです。死後事務や遺産分割協議の疲れでうっかり安易な判断を下しがちですが、少なくとも申告書の提出要否だけはきちんと確認しましょう。
申告要否の簡易判定シートを活用する
税の情報について国税庁が案内するサイトでは、相続税の申告要否の簡易判定シートが公開されています。法定相続人やおおよその財産の情報を書き込み、申告書の提出が必要かどうか判断するためのものです。
注意したいのは、課税遺産総額と基礎控除に基づく簡易判定になる点です。生前贈与や評価減のある財産があるケースでは、個別の案内でないと確実な答えは得られません。
後から申告書の提出義務に気付いた時は
後になって相続税の申告義務があると気付いた場合は、すぐに所定の様式で税務署に届け出ましょう。
期限後申告と呼ばれる上記対応は、申告漏れに気付いた税務署が課税額の決定(=更正の決定)を下すまでなら、いつでも実施できます。そうは言っても、無申告の状態でいつまでも放置してはおけません。
無申告のままにしてはいけない理由
相続税申告書の提出義務を果たさない場合、発覚するとペナルティがあります。取得した財産に対する課税分だけでなく、一定の割合で「無申告加算税」と「延滞税」を上乗せして納付しなければなりません。無申告加算税だけでも15%(50万円を超える部分は20%)に及び、延滞税に至っては、納期限後2か月目から最大年14.6%の利率で加算され続けます。
税務調査等で発覚する前に自主的な期限後申告を行えば、無申告加算税の割合につき5%の軽減があります。納付が1日でも早まれば、無駄な延滞税も負担せずに済むでしょう。
❏まとめ│相続税申告の要否は専門家に最終チェックしてもらう
納付すべき額がゼロであったとしても、相続税の申告書を出さなくていいわけではありません。申告不要と断定する前に、課税額の計算過程を改めて振り返ってみましょう。
・課税遺産総額は正確か?
・「配偶者の税額の軽減」の適用はないか?
・「小規模宅地等の特例」の適用はないか?
・「事業承継税制」等の納税猶予制度の適用はないか?
申告義務に気付かずに期限を過ぎてしまうと、無申告扱いで追徴課税の対象になってしまいます。本記事では加算税と延滞税のみ紹介しましたが、期限内申告が適用条件になっている特例を使うつもりだったケースでは、取得財産に対する課税分自体が想定を大幅に上回ってしまう可能性があります。
以上のリスクを念頭に、相続税の申告義務について少しでもあやふやな点があれば、早めにソレイユ相続相談室へのご相談をおすすめします。
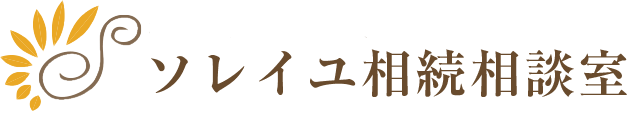

![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/i3yJKUMIzTRrl5P5ZZwwE72aLnQPaJNKyCHscKlV.png)
![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/e1LEOFAUxAAEyA54anKQHuSbRHnk8oBBDc98qad2.png)




![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/uploads/Header/YBinHyDM8hpRvWbTTFZXCAFHOfS8wEI3m6twFq0Q.png)