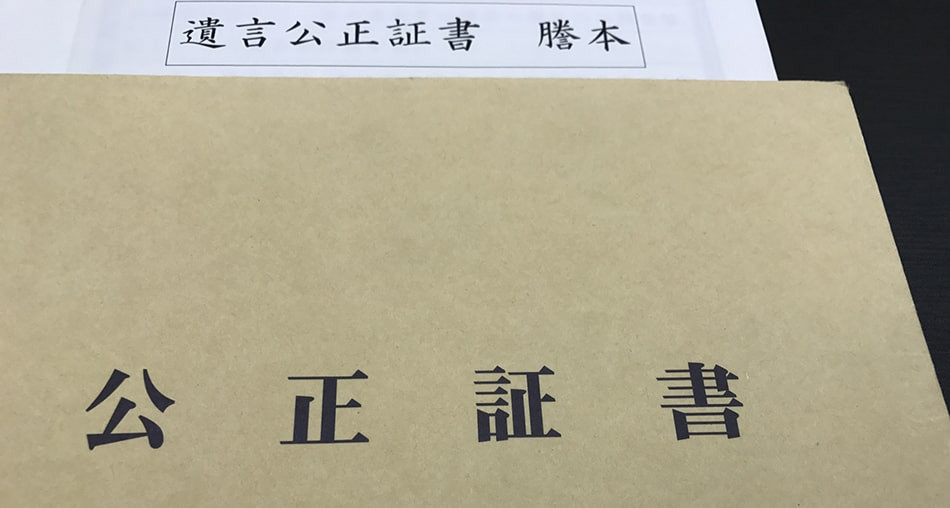中小企業の経営をサポート!中小企業経営承継円滑法 民法特例とは

 日本の経済を支えてくれている企業の多くは「中小企業」です。日本の総企業数の99%は中小企業という現状であり、その多くが家族経営で成り立っています。
日本の経済を支えてくれている企業の多くは「中小企業」です。日本の総企業数の99%は中小企業という現状であり、その多くが家族経営で成り立っています。
家族内で事業を承継していくことも大変多く、相続や贈与といった手続きによって個人の財産だけではなく、経営自体も次世代に引き継ぎを行います。
しかし、相続や贈与には税金が重くのしかかってくるため、事業承継に難航した挙句、廃業という形で経営の灯を吹き消してしまうケースもあります。
そこで、日本を支える経営の灯を支えるために「中小企業経営承継円滑法」という法律が施行されています。今回の記事では、この法律の「民法特例」に注目して詳しく解説します。
中小企業経営承継円滑法とはどんな法律か?
日本の経済を支える多数の中小企業は、高齢化社会を背景に事業承継に悩まされている現状があります。家族が大切に育ててきた会社を受け継ぎたい、そんな思いがあっても重い税負担の前では悩んでしまう方も多いでしょう。会社の資金繰り状況や課税を客観的に見つめると、「廃業」という選択をする方もいます。
そこで、中小企業の円滑な経営を、国を挙げてサポートするために「中小企業経営承継円滑法」と呼ばれる法律が2008年10月に施行されました。
この法律は事業の承継時に問題となりやすい3つのポイントを法的に対応しています。
事業の承継時に問題点となりやすい3つのポイントとは
中小企業の経営で次世代の経営者へとバトンタッチをする場合には以下の3つが事業承継を閉ざしかねない問題として存在しています。
1.贈与税や相続税
事業を承継する際には、贈与税や相続税という税負担が重くのしかかります。
2.事業承継時の資金調達
事業を承継する際にはさまざまな手続きが必要となります。代表的な手続きとして自社株の購入などが考えられます。この際に資金調達に難航するケースがあるのです。
3.民法上の遺留分による制約(民法特例)
相続が発生してから事業承継を行う際には、遺留分が気になるところです。例えば生前、経営者だった父が良かれと思って長男へ事業承継に関する相続を集中させる内容の遺言書を残していたと仮定しましょう。しかし、死去後に株や不動産の価値の上昇していたことが判明すると、長男以外の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。相続ならではの制約が、事業承継の前にも重く横たわっているのです。
遺留分とは? 知っておきたい民法特例
上記で解説のとおり、中小企業経営承継円滑化法では遺留分に配慮をした「民法特例」が制度化されています。では、ここからは遺留分とは何か、民法特例とは何かについて詳しく解説しましょう。
今こそ遺留分について学ぼう!
相続をする場合、法定相続人に対して相続の割合が民法上で定められています。配偶者には2分の1…などの割合が決められていることは広く知られていますね。遺留分とはこの割合と誤解をされがちですが、そうではありません。遺留分とは「最低限もらえる相続財産の割合」のことです。相続によってはある特定の相続人に財産が集中しすぎる場合があります。特に事業承継の場面では、次期経営者に内定している方に大きな財産が集中し、その他の相続人は財産がもらえない可能性があります。そんな時には「最低限の財産は相続できる」と民法上で定められており、この割合を遺留分と言うのです。
民法特例とはどんな制度か?
中小企業経営承継円滑法では民法特例と呼ばれる制度が定められています。民法特例とは事業承継時に、遺留分が負担となり過ぎないように設定している制度です。遺留分が気になって事業承継ができない…そんなトラブルを防ぐために「遺留分を求めることができる推定相続人(※1)と会社を継ぐ相続人の全員の合意」を得ることで民法特例を受けることができます。平成28年4月1日はもっと事業承継を行いやすくするために、推定相続人以外も合意があれば対象者となりました。つまり、親族以外の方への承継も対象に入ります。では、民法特例とはどんな制度なのでしょうか。
1.除外合意とは
除外合意は経営を引き継ぐ自社の株式について、遺留分の請求(遺留分減殺請求※2)対象から除外するという合意です。つまり、次期経営者とその他の相続人の間で相続バトルが発生し、遺留分を求めることになっても算定される相続財産から除くことができます。個人事業の場合には事業資産の価額を除くことが可能です。大切な事業の財産を守ることができるのですね。
2.固定合意とは
固定合意は除外合意とは異なり、まずは自社の株式は遺留分の請求時には算定される財産に入れるものの、全員の合意の下で評価額を固定できる、という合意です。もしも会社経営が好調でどんどん株式の評価が上がっても、評価は固定されているので固定時以上に遺留分の請求を受けることがありません。みんなで財産を分け合い、会社も守ることができます。
(※1)遺留分が請求できる推定相続人
遺留分が推定できる相続人は民法上で定められており、亡くなられた被相続人の配偶者。直系尊属である両親等、直系卑属である子が認められています。被相続人から見た兄弟姉妹は認められていません。この記事では相続開始まで相続人ではないため、推定相続人として解説しています。
(※2)遺留分減殺請求
相続で自身の遺留分を侵害される場合には、遺留分減殺請求を行うことができます。この制度は当事者間の話し合いで解決を図りますが、解決が難しい場合に家庭裁判所で調停も可能です。家事事件ですが調停不成立の場合は民事訴訟に移行する必要があります。
民法特例をもっとお得に活かそう!事業承継を乗り越えるコツ
民法特例は平成28年には親族以外の事業承継に関しても対象となりました。元々この法律は親族の相続と事業承継に重きを置いて施行されていましたが、事業承継の形態が多様化したことから柔軟にすべく法改正を行ったのです。中小企業庁によると、現在中小企業の親族外承継が約4割となっており増加傾向です。では、この民法特例を活かすにはどうすれば良いのでしょうか。ここからは適用するための手続きをご紹介します。
参考記事はコチラ→ 中小企業庁 「承継円滑法が本日施行されました」
民法特例を使う方法とは 流れと条件を知ろう!
民法特例を活用するには以下のような適用条件をクリアしましょう。
1.会社の場合
中業企業のみが適用可能であり、合意の時点で3年以上経営を続けている非上場企業が適用条件です。先代経営者は合意に至るまでは会社の代表者である必要があり、バトンタッチ後に遡って民法特例を使うことはできません。早くから民法特例について把握し、合意を目指して活動を開始することが重要です。後継する方(推定相続人以外も可能)は会社の議決権を過半数以上有している必要があります。
2.個人事業の場合
合意の時点で3年以上事業を経営しており、後継者に事業用の財産を贈与したことが条件になります。株式のやり取りではないので、事業用財産が動くことが条件です。
適用するための手順とは?
将来相続時に遺留分を引き金とするトラブルに発展しないためにも、合意形成を行い明るい事業承継を目指したいですよね。そこで、最後に適用する手順を解説します。
1.合意書の作成
先に触れた2つの合意のどちらにするのか推定相続人と次期経営者の間で合意を行う。
2.経済産業大臣の確認
合意形成が完了した後には、1か月以内に「遺留分に関する民法の特例に関わる確認申請書」と登記事項証明書などの必要書類をセットして申請する。
3.家庭裁判所へ申立て
遺留分に関する分野のため、経済産業省による確認を終えたら1か月以内に申立てを行います。申立てに不備が無ければ許可が下ります。
参考記事はコチラ→中小企業庁 事業承継と民法<遺留分>
まとめ
この記事では中小企業の明日を守る「中小企業経営承継円滑法」について、民法特例に焦点を当てて詳しく解説を行いました。事業承継の際には次期経営者以外の推定相続人にも気を配りつつ、合意書をしっかりと作ることで遺留分トラブルを防ぐことができます。
合意に関するご内容や制度の詳しい内容、必要書類のアドバイスに関してソレイユ相続相談室では皆様のご要望に柔軟に対応しております。日本を支える経営の灯を、一緒に守っていきませんか。
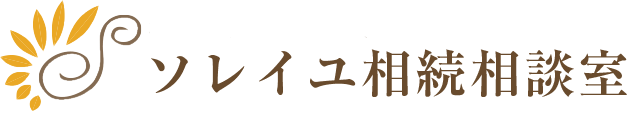

![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/i3yJKUMIzTRrl5P5ZZwwE72aLnQPaJNKyCHscKlV.png)
![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/e1LEOFAUxAAEyA54anKQHuSbRHnk8oBBDc98qad2.png)




![【ソレイユ相続相談室】相続税,家族信託,遺言,相続手続き,相続対策専門の税理士と行政書士が運営・監修する相続サイト[初回相談無料]](https://soleil-confiance.co.jp/public/uploads/Header/YBinHyDM8hpRvWbTTFZXCAFHOfS8wEI3m6twFq0Q.png)